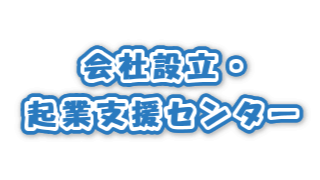飲酒運転に対する社会の目が厳しくなっていて、自動車運転代行に対するニーズが高まっています。
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する営業で以下のすべてに該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するサービスを提供するもの
- 酔客など運転代行サービスの提供を受ける者を乗車させるもの
- 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するもの
自動車運転代行業の開業には公安委員会の認定が必要
自動車運転代行業を開業するには、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定後、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
自動車運転代行業の認定申請手続きの流れ
- 欠格要件の確認欠格要件に該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
欠格要件に該当していないことを確認します。
※欠格要件に該当する場合は、認定を申請しても拒否されます。 - 申請書類の準備申請書の作成と添付書類の取得をします。
- 申請書の提出営業所の所在地を管轄する警察署に申請書を提出します。
認定申請手数料12,000円が必要です。
※欠格要件に該当する場合は、認定は拒否されます。認定を拒否された場合、認定申請手数料は返金されません。 - 警察署による審査都道府県公安委員会の審査を受けます。
- 認定証の交付申請書を提出した警察署で認定証の交付を受けます。
- 営業開始随伴用自動車に車体表示などを行ない、営業を開始します。
認定を受けることができない人
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が上記1.~5.および下記9.のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(※2)
- 安全運転管理者(※1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
- 法人でその役員のうち上記1.~5.までのいずれかに該当する者があるもの
申請に必要な書類
申請書
申請書への記載内容は、次のとおりです。
- 申請者の住所及び氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 安全運転管理者(※1)の氏名
(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する) - 損害賠償措置(※2)
- 随伴用自動車の自動車登録番号
- 認定を受けようとするものが法人の場合
役員の住所及び氏名
添付書類
都道府県によって異なることがあります。
| 添付書類 | 個人申請 | 法人申請 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住民票の写し | ○ | ○ | 役員全員分 |
| 精神機能の障害に関する医師の診断書及び誓約書 | ○ | ○ | 役員全員分 |
| 法人の登記事項証明書 | × | ○ | |
| 定款又はこれに代わる書類 | × | ○ | |
| 役員名簿 (氏名及び住所が記載されたもの) |
× | ○ | 役員全員分 |
| 損害賠償措置を証する書類(※2) | ○ | ○ | |
| 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(※1) | ○ | ○ | |
| 随伴車両の車検証の写し | ○ | ○ | |
| (申請者が未成年者の場合) 未成年者登記事項証明書 法定代理人に関するもの |
○ | × |
※1 自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
| 随伴用自動車の台数(台) | 副安全運転管理者の人数(人) |
|---|---|
| ~9 | 0 |
| 10~19 | 1 |
| 20~29 | 2 |
| 30~39 | 3 |
| 40~49 | 4 |
※2 損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により以下の額を最低補償額として満たしていなければなりません。
- 対人:8,000万円
- 対物:200万円
- 車両:200万円
自動車運転代行業の営業方法
自動車運転代行業を開業して営業する方法としては、以下のことが考えられます。
- 折り込み広告・ポスター
- インターネットの活用(自社ホームページやポータルサイトへの登録)
自動車運転代行業を始めるなら法人がお勧めです
個人事業で自動車運転代行業を始めて、後々法人化しようと思ったら、その時点で改めて認定の申請が必要になります。
その際には、保険の付け替えや随伴車両の車体表示の変更など面倒なことが発生します。
後々法人化する可能性があるのなら、最初から法人化しておくことをお勧めします。
自動車運転代行業を開業するなら作っておきたい法人ガソリンカード
自動車運転代行業で開業すると、頻繁に燃料を入れるようになるでしょう。その都度、現金で支払うのは面倒だと思いませんか?
事業用のガソリンカードを1枚作っておいたら、そんな面倒から解放されます。
自動車運転代行業にお勧めのガソリンカードはこちらをご覧ください。
> 新設会社におすすめのガソリンカード